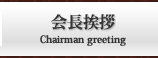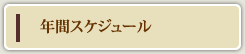第4回例会 「都市工学から見た名古屋の成り立ち」
2014.10.24
都市工学から見た名古屋の成り立ち
10月24日、ガーデンレストラン徳川園において第4回例会「都市工学から見た名古屋の成り立ち」が参加者72名にて開催されました。
三厨事業委員の司会により亀井会長の挨拶後、若鯱会・阿部代表幹事の挨拶がありました。続いて本日の講師、名古屋学院大学 経済学部教授 井澤 知旦(いざわ ともかず)氏の紹介がありました。
講師のユーモアあふれる自己紹介から始まり、名古屋まちづくり史〜江戸から現代まで〜 と言うテーマの中「紀元前4,000年前の名古屋の地形は、現在の名古屋城から熱田付近までは大陸であったが、名古屋駅周辺は、そのほとんどが海だった」と驚愕の事実から講演がスタートしました。
江戸時代は、大火の度に通りの拡張の区画整理が計画的に行われた時代でした。3間幅の筋が、15間の「広小路」となり、5間幅の「本町通り」、4間幅の四間道の整備と、現在の道筋の基本計画がなされました。明治に入ると、鉄道の開通や延伸により都市基盤の整備が行われました。昭和は38回にもおよぶ空襲で、名古屋の面積の半数以上が延焼し、戦災復興から都市の整備がスタートしました。しかし、江戸時代や明治時代の都市整備の経験から、他の都市と比べていち早く道路等のインフラ整備が進み、そして100m道路などの大胆な計画により震災復興を成し遂げました。
町名やバス停の名前で、そこが以前はどのような地形だったかのヒントとなるなど、関西弁特有のユーモアある話し口で、最初から最後まで聴く者を引き付ける独特の語り口が印象に残る講師でした。更に、懐かしい名古屋の町並みを映像で見ながら、「あ、あの看板昔・・・あったネ。」「そうそう、あのビルあったは、・・・。」と若き日の自らも思いおこし、拍手・拍手と鳴り止まぬ拍手で講演が終了しました。
安井事業委員長の謝辞の後、同じ会場にて懇親会が行われました。大口雅章氏の乾杯の音頭で宴が始まり、和気藹々の楽しい雰囲気の中、中川副会長の中締めでお開きとなりました。
安井委員長、そして事業委員会の皆様、楽しい例会を有り難うございました。
(記事投稿:小林広報委員 写真:後藤委員長、永田委員、中村委員、近藤委員)
<講演会>
 司会の三厨委員
司会の三厨委員 亀井会長の挨拶
亀井会長の挨拶 若鯱会 阿部代表幹事の挨拶
若鯱会 阿部代表幹事の挨拶 講師の井澤先生
講師の井澤先生 ユニークな自己紹介
ユニークな自己紹介 紀元前4000年の名古屋
紀元前4000年の名古屋 ユーモア溢れる講演
ユーモア溢れる講演 名古屋発展の歴史
名古屋発展の歴史 会場風景
会場風景 謝辞を述べる安井委員長
謝辞を述べる安井委員長
懇親会
 乾杯のご発声 大口雅章氏
乾杯のご発声 大口雅章氏 懇親会風景
懇親会風景 中川副会長の中締め
中川副会長の中締め 会場の中締め風景
会場の中締め風景